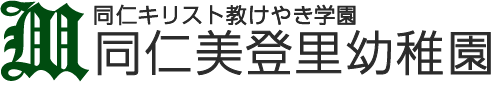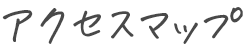みなさんこんにちは。毎日暑いですね。
暑すぎて三年坂を登るのが毎日きついです。大塚警察署のところから幼稚園までエスカレーターができてほしい。
さて、夕涼み会です。
同仁美登里カルチャーに初めて触れる親御さんたちにとって、初見で何をするのか全く想像がつかないイベントのベスト3に入るこの「夕涼み会」(一位はページェント)、本日は年少組参加者の視点からレポートして参りたいと思います。
この日は午前で幼稚園は終わり。それぞれチケットが配られ、交換するとお店屋さんの催し物や、お店で品物と交換してもらえます。等価交換は貨幣経済の原理原則、金融教育のファーストステップですね(個人の見解です。幼稚園としてその意図があるかどうかは分かりません)。
娘の喜びようったらなく、通り過ぎる同仁美登里っ子たちに「今日は夕涼み会だよ!」と逐一声をかけながら帰りました。
暮れなずむ街の光る風の中、いよいよ「夕涼み会」が始まりました。

浴衣姿・甚兵衛姿のかわいらしい子供たちが集います。いつもと違う装いが新鮮で、目にするだけで涼を感じます。
先生たちの浴衣姿も涼しそう。

夕涼み会といえば、最大の見どころは年長組のお兄さん・お姉さんたちによる「お店屋さん」です。
年長組さんが先生と一緒に企画を考え、制作し、販売までしているんです。
射的、水鉄砲ゲーム、うちわ屋さん、てづくりひん屋さん、お菓子ジュース屋さん…と並んでいるだけでワクワクしそうな露店が幼稚園のお庭に並んでいます。
お店のスタッフは、年長組さんの子供たち。ジュースの買い出しまで、自分たちで行ったそう!

射的。
うまいこと筒が飛ぶように作られています。完成度の高さに脱帽です。
「のぼり」はもちろん、ゲームのルール説明の看板なども自分たちで作ったそう。本格的です!

てづくりひん屋さんでは、ヘアアクセサリーやパックン、ポシェットなど素敵な品物が並びます。
全部手作りだそう。
クオリティが高くびっくりしました!

うちわ屋さん。うちわの柄は年中組さんにも手伝ってもらって作ったそうです。売り子さんの姿もサマになっていますね。
さて、ここでインシデントが発生しました。
娘は最初にてづくりひん屋さんでヘアゴムを手に入れた後「やっぱりポシェットがいい。変えてもらう」と言って戻り、ポシェットを選んだのですが、後で「やっぱりパックンがいい!もう一回行って、変えてもらう!」と言い出したのです。
親としては、ここで50個くらい考えが浮かぶわけです。
「なんでやねん」
「2回も交換ってどうなん」
「親としては、自分の発言に責任を持つことを教えるために、選んだもので我慢するよう言うべきでは?」
「でも気に入らないものを持って帰って使わなければむしろ地球環境にとっても作ってくれた人にとってもよろしくないのでは」
「まあでも娘の希望は叶えてやりたい」
「ここで泣かれたらとってもメンドクサイ」
「しかしまた列に並ぶのもメンドイ」
「娘には交渉して自分の欲しいものを手に入れる力をつけてほしい」
……などなど、考えた結果
「いいけど、ママここで見てるから、自分で行ってお姉さんと交渉してきな」と送り出しました。
お店のお姉さんに「え!また来たの!」と言われながら(ごもっともです)勇気を振り絞って「変えて」と言えた娘。 てづくりひん屋さん担当の先生も苦笑しつつ「いいよ」と言ってくれたので最終的に欲しいものを手に入れたのですが、親としてはこの指導でよかったのかどうか。
ゲームだったらこれでパラメーターが「ピコン!」となって「おー、成長した」となるわけですが、
現実の育児はなぁんもわからんわけです。
子育ては日々秒単位でやってくる選択と葛藤と決断の繰り返し、しかもその答え合わせは10数年後、下手したら数十年後かもしれないわけで、一生かけて答えが分かる壮大なクイズみたいなもんなわけで……。
日々「わからん」の中で生きております。

さて話がずれましたが、なんと言っても、夕涼み会で感動したことは、年長組のお兄さん・お姉さんの勇姿だったわけです。

年長組のお兄さん、お姉さんによるアナウンス(緊張しつつも、大きな声ではっきりとアナウンスしていて、その堂々ぶりに感銘を受けました)
射的やゲームでも「こうやってやるんだよ」と年下のお客さんに丁寧に説明したり、商品を渡してあげたりと、頼もしい姿が見られました。
普段の園生活では、なかなか他の学年の子たちと接する機会は少なく、年長組さん、年中組さんがどんなふうに過ごしているのか知ることはできません。
ですが、夕涼み会のために一生懸命出し物を考え、お店を出し、説明をし、チケットを受け取り、アナウンスをし……。という姿を見ているだけで、この日のために彼らがどれだけ頑張って考えてきたのかが伝わり「5歳になるとこんなことまでできるのか」「もう社会的生物だな(いや、赤ちゃんも社会的生物ではあるんですが、より主体的に参加しているという意味で)」としみじみしました。
これだけの事を自分たちで決めるというのは、葛藤や悩みもあったでしょうが、それをやり遂げたみどり組の子供たちの勇姿から、親として力を分けてもらったような気がします。
そんなわけで、夕涼み会は出し物を楽しむとともに、2年先の我が子の姿に思いを馳せ、楽しみになる会でもありました。
年長組のみなさん、先生方、お疲れ様でした!
(年少組保護者 P.N母のはしくれ)